【時代の流れ?】紅白歌合戦、過去ワースト視聴率!その理由は…
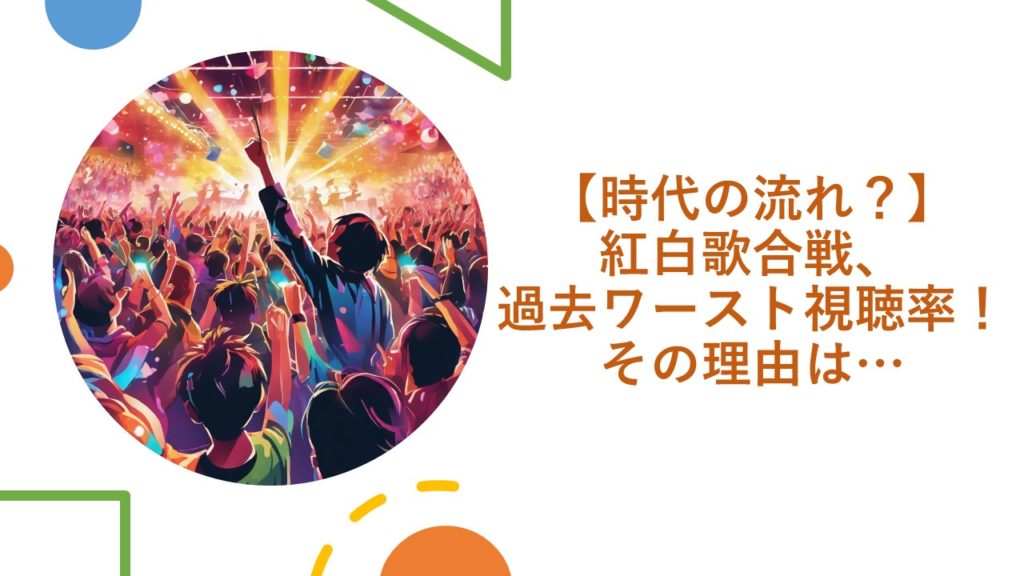
目次
紅白歌合戦の人気の変化

ムームードメイン様々な趣向を凝らした紅白歌合戦だったが…© (C) スポーツニッポン新聞社
昨年大晦日に放送された「第74回NHK紅白歌合戦」の平均世帯視聴率は、第2部(午後9時)で関東地区は31.9%となり、過去最低記録となりました。これはビデオリサーチによる調査結果です。21年の視聴率である34.3%から2.4ポイント低下しました。関西地区では32.5%でした。第1部でも関西地区では27.5%、全体でも29.0%と、初めて30%を下回りました。今回は旧ジャニーズ事務所所属の出場者がいなかったことも注目されました。番組の司会は有吉弘行さん、橋本環奈さん、浜辺美波さん、高瀬耕造アナウンサーが務め、多くのK-POP勢が出演しました。企画コーナーではNew JeansやYOSHIKIさんも登場しました。後半ではYOASOBIが世界的なヒット曲「アイドル」を日本の音楽番組で初めて披露しました。優勝は紅組でした。
さらに、裏番組の成功も影響を与えました。TBSの「WBC2023 ザ・ファイナル」では、午後7時から11時45分までの第3部が8・9%の視聴率を記録しました。前年の「THE鬼タイジ」の5・4%から大幅に数値が上昇しました。また、テレビ朝日の「ザワつく!大晦日 一茂良純ちさ子の会」は3年連続で民放トップの視聴率を獲得しました。午後6時から7時30分までの第2部は12・3%で、こちらも前年の10・0%から2ポイント以上上昇しました。
TBSのWBC特番は、生放送でしたが、放送時間の大部分は大会の映像で構成されていました。 "ザワつく..."は収録でしたが、62歳の栗山英樹氏がゲスト出演した事も話題になりました。放送関係者は、「これまで紅白を生放送で楽しんでいた年配の人々の視聴率も、大谷WBCに取られたのではないか」と推測しています。
最近、見逃し配信などの視聴環境の変化により、世帯視聴率は減少傾向にあります。その一方で、NHK関係者は「民放でも年末の音楽特番の視聴率がほぼ2ポイント下がっていました。旧ジャニーズの不在も影響しており、紅白も数字が下がることを予測していましたが、思いがけぬ裏番組への視聴者の流れもあることに落胆しています」と述べ、予想以上の減少に失望しています。
「テレビ朝日は2日、ビデオリサーチによる2023年の年間世帯視聴率(関東地区)において、午前6時から翌日午前0時までの全日の視聴率が6.4%、午後7時から10時のゴールデンタイムの視聴率が9.1%、午後7時から11時のプライムタイムの視聴率が9.3%となり、それぞれ首位を獲得し、「3冠」を達成しました。同じ時間帯における2位は日本テレビで、全日の視聴率は6.1%、ゴールデンタイムは8.8%、プライムタイムは8.4%になりました。」
紅白歌合戦は日本の年末恒例の音楽番組であり、長い間視聴者に愛されてきました。しかし、最近の視聴率の低下により、人気に変化が生じています。
紅白歌合戦の魅力の変化
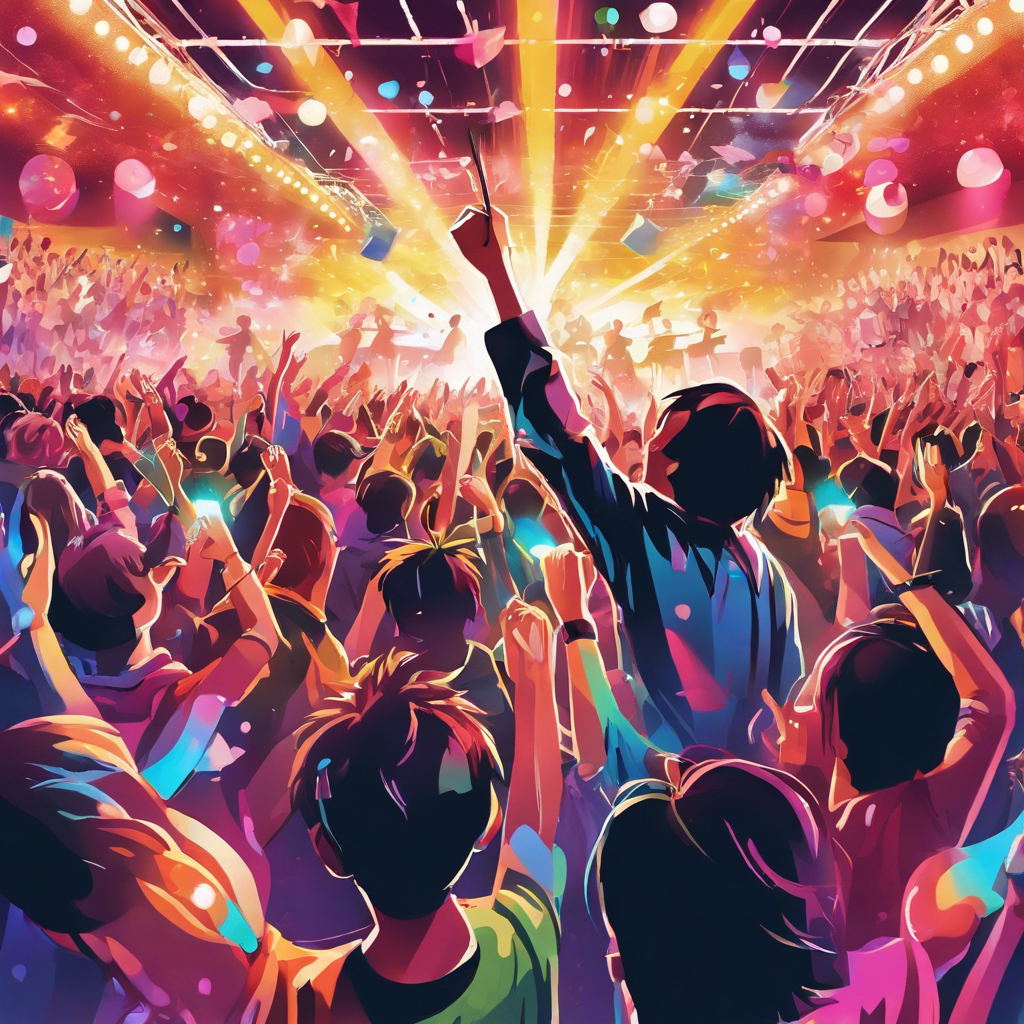
紅白歌合戦は、1951年にNHKが放送を開始した、日本の音楽番組の最高峰として知られています。毎年12月31日に放送され、日本の音楽シーンを代表する歌手やアイドルが一堂に会し、歌を披露する番組です。
紅白歌合戦の魅力は、大きく分けて3つあります。
1、日本の音楽シーンの総決算として、その年のヒット曲や注目のアーティストが一堂に会する点です。紅白歌合戦に出演することは、日本の歌手やアイドルにとって大きなステータスであり、その年の音楽シーンを振り返る上で欠かせない番組となっています。
2、世代を超えて親しまれる番組である点です。紅白歌合戦は、1951年の放送開始以来、長年にわたって国民的な番組として親しまれてきました。そのため、老若男女を問わず、幅広い世代の視聴者に支持されています。
3、華やかな演出やパフォーマンスが楽しめる点です。紅白歌合戦では、豪華なセットや衣装、演出によって、歌のパフォーマンスがより一層引き立てられます。また、コラボレーションや特別企画など、毎年新しい試みが行われるのも、紅白歌合戦の魅力の一つです。
しかし、近年では、それぞれのファン層や音楽の好みの多様化により、一つの番組で全ての視聴者のニーズを満たすことが難しくなってきました。
例えば、若い世代の視聴者は、アイドルやK-POPアーティストの活躍に注目しており、演歌や歌謡曲を好む視聴者は、近年減少傾向にあります。また、音楽のジャンルも、J-POPだけでなく、洋楽やアニメソング、ボカロ曲など、多様化しています。
そのため、紅白歌合戦では、近年、若手アーティストやK-POPアーティストの出演を増やすなど、視聴者のニーズに合わせた工夫が行われています。また、音楽ジャンルの垣根を越えたコラボレーションや、特別企画なども積極的に行われており、番組の魅力を維持するために、さまざまな試みが行われています。
今後も、紅白歌合戦が日本の音楽シーンを代表する番組として、長く愛され続けるためには、時代の変化に合わせた新たな魅力を創造していくことが求められるでしょう。
紅白歌合戦の視聴率の推移

| 年度 | 第1部の平均視聴率 | 第2部の平均視聴率 |
|---|---|---|
| 2021年 | 31.5% | 34.3% |
| 2022年 | 31.2% | 35.3% |
| 2023年 | 29.0% | 31.9% |
過去数年間の視聴率を見ると、第1部の視聴率は比較的安定していますが、第2部の視聴率は2021年をピークに減少傾向にあります。特に2023年の視聴率は過去最低となりました。
最近の視聴率の低下
紅白歌合戦は長い間、多くの視聴者に支持されてきた人気のある番組でしたが、最近では視聴率の低下が見られます。この低下はいくつかの要因によるものであり、番組の魅力や視聴者の嗜好の変化が関係しています。
紅白歌合戦の近年の視聴率の下降要因
最初に考えられる要因は、番組の魅力の減少です。過去に比べて、視聴者が番組に対して興味を持ちにくくなった可能性があります。また、他のエンターテイメントコンテンツへの需要の高まりも視聴率低下の要因として挙げられます。
第72回(2021年)
2021年の大みそかの紅白歌合戦第2部の平均世帯視聴率は、過去最低の34.3%となりました。別の調査によると、テレビを見ている人たちの中で、「紅白」を視聴している人の割合が非常に高くなっていたそうです。つまり、大晦日の夜にテレビをつけず、ネット動画を見るなど別のことをする人が増えたために、視聴率が下がったというのが真実のようです。
第73回(2022年)
2022年の「第73回NHK紅白歌合戦」は、3年ぶりにNHKホールで有観客が入ることとなった。視聴率は第2部(午後9時)で、関東地区が35.3%(関西地区が36.7%)であった。前年の34.3%より1ポイント上昇したが、過去最低の記録であり、ワースト2となった。出場歌手には、韓国の人気グループなどの初出場組が多く投入され、若者層を意識していた。一方で、中高年層を意識した松任谷由実(68歳)、加山雄三(85歳)、安全地帯、桑田佳祐(66歳)率いる「同級生バンド」といったメンバーも特別枠で参加した。また、歌手活動休止前の氷川きよし(45歳)も話題になった。しかし、期待されていた40%以上の大台には到達せず、微増に留まった。
テレビ番組に詳しいコラムニストの桧山珠美さんは、「特別企画は8つもあり、その出演者の方が若者向けの通常の出場歌手よりも格上に見え、豪華な付録がついているため、雑誌を買わせるような印象を受けます。特別企画やゲストのトークが増えた結果、本来最も重要なはずの歌を聴く時間が削られている」と指摘しています(読売オンライン、2023年1月5日)。
現在の視聴率測定方法では、録画やスマホなどのストリーミング視聴がカウントされていないという意見があります。これは「音楽のCD売り上げ枚数を比較するのと同じで、過去との比較にはあまり意味がない」とも言われています。
第74回(2023年)
2023年の大晦日に行われた「第74回NHK紅白歌合戦」は、国外メディアによって公になった創始者の性的虐待問題のため、旧ジャニーズ事務所の出演がなかったことから、注目されることとなった。この番組の第2部(午後9時)の平均世帯視聴率は、関東地区で31.9%(関西地区では32.5%)であり、過去最低の21年の34.3%から2.4ポイント下がり、過去最低の視聴率となった。
今回のテーマは「ボーダレス」です。総合司会は有吉弘行さんと橋本環奈さん、浜辺美波さん、そして同局の高瀬耕造アナウンサーが務めました。音楽ユニット「YOASOBI」が去年最もヒットした曲「アイドル」を国内の音楽番組で初めて歌いました。そして、素顔を出さない「歌い手」のAdoさんは、京都・東本願寺の能舞台からのサプライズ中継を行いました。
特別企画では、内村光良、千秋、ウド鈴木によるユニット「ポケットビスケッツ」と、ビビアン・スー、南原清隆、天野ひろゆきによる「ブラックビスケッツ」が25年ぶりに出場して番組を盛り上げた。デビュー50周年の3人組アイドル「キャンディーズ」のメンバーで女優の伊藤蘭は、46年ぶりの出場となった。 特別企画では、内村光良さん、千秋さん、ウド鈴木さんによるユニット「ポケットビスケッツ」と、ビビアン・スーさん、南原清隆さん、天野ひろゆきさんによる「ブラックビスケッツ」が25年ぶりに出演して番組を盛り上げました。デビュー50周年の3人組アイドル「キャンディーズ」のメンバーで女優の伊藤蘭さんは、46年ぶりの出演となりました。
また、かつてのジャニーズ事務所(現在のスマイルアップ)は、ジャニー喜多川氏(2019年に亡くなった)による性被害問題に揺れています。このため、前年の6組から44年ぶりに出場者がゼロとなりました。人気のある男性グループであるJO1やBE:FIRSTに加えて、韓国のグループであるStray KidsやSEVENTEENの出場も目立ちました(スポーツ報知)。
ジャニーズ勢の不在と視聴率

旧ジャニーズ勢の不在は、その影響のひとつです。昨年、出場した6組のうち、Snow Man、SixTONESなど4組は同じ時間帯に生配信を行い、"ライバル"となりました。同局の関係者は、「これまでジャニーズグループを目当てに紅白を見ていたファンが一気に離れた」と指摘しました。
新たな視聴習慣の浸透
紅白歌合戦のイベント性の減少には、以下の要因が考えられます。
テレビ離れの進展
近年、若年層を中心にテレビ離れが進んでいます。そのため、紅白歌合戦の視聴者層も高齢化が進んでおり、イベント性を感じにくくなっていると考えられます。
インターネットや動画配信サービスの普及
インターネットや動画配信サービスの普及により、好きな音楽を好きな時間に好きなだけ視聴できるようになりました。そのため、大晦日の夜にわざわざテレビの前で紅白歌合戦を視聴する理由が薄れてきていると考えられます。
番組内容の変化
近年、紅白歌合戦では、視聴率を獲得するために、アイドルやK-POPアーティストの出演を増やす傾向にあります。しかし、これらのアーティストは、演歌や歌謡曲を好む視聴者にとって馴染みが薄く、イベント性を感じにくいという意見もあります。
こうした要因により、紅白歌合戦のイベント性は徐々に減少しています。今後も視聴率を維持するためには、番組内容の見直しや、新たな魅力の創出が求められるでしょう。
エンターテイメント業界の変動
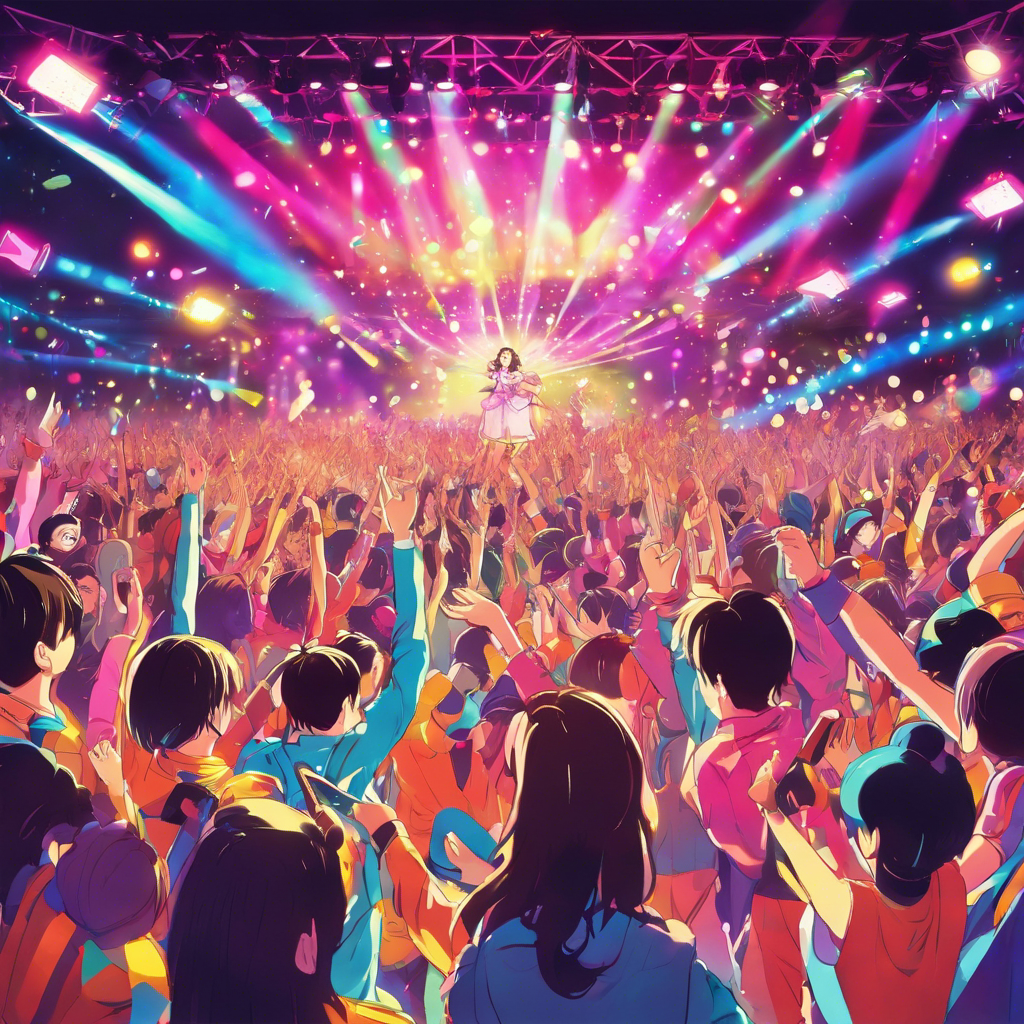
紅白歌合戦の視聴率低下の背景には、エンターテイメント業界の変動も大きく影響しています。
近年、エンターテイメント業界では、テレビ離れの進展やインターネットや動画配信サービスの普及など、さまざまな変化が起きています。
その結果、従来のテレビ番組の視聴者層は高齢化が進み、若年層の視聴者が減少しています。
紅白歌合戦も例外ではなく、若年層の視聴者離れが進んでいると考えられます。
また、エンターテイメント業界では、アイドルやK-POPアーティストなどの若手アーティストの台頭が著しくなっています。
これらのアーティストは、インターネットや動画配信サービスを中心に活躍しており、テレビ番組への出演にそれほどこだわっていない傾向があります。
そのため、紅白歌合戦への出場を辞退するアーティストも増えています。
また、旧ジャニーズ事務所の出場ゼロは、紅白歌合戦にとって大きな痛手となりました。
旧ジャニーズ事務所のアーティストは、紅白歌合戦の伝統的なパフォーマンスを担ってきた存在であり、その不在は視聴者の関心や期待の低下に繋がったと考えられます。
一方で、韓国勢や初出場組の台頭は、紅白歌合戦に新たな魅力をもたらしています。
これらのアーティストの新鮮さや個性的なパフォーマンスは、従来の視聴者層だけでなく、若年層の視聴者にも人気を集めています。
しかし、若手アーティストが主役となり、紅白歌合戦の伝統的なイメージから一線を画すようになったことも、視聴率の低下に一因となった可能性があります。
今後も、エンターテイメント業界の変動は続くと考えられます。
紅白歌合戦が日本の音楽シーンを代表する番組として、長く愛され続けるためには、時代の変化に合わせた新たな魅力の創造と、視聴者のニーズに合わせた番組内容の見直しが求められるでしょう。
まとめ
過去ワースト視聴率の原因のまとめ
紅白歌合戦の視聴率が過去ワーストとなった要因は、旧ジャニーズ事務所の出場のないことや若手アーティストの台頭、ネット上の反応の影響などが考えられます。これらの要素が重なり、視聴者の関心や期待が減少し、視聴率の低下に繋がったのでしょう。
紅白歌合戦の将来展望
紅白歌合戦は長い歴史を持つ日本の音楽イベントであり、その伝統を守りながら新しい試みを行う必要があります。アーティストの選択や出演形式の変化によって、視聴者への魅力を再度高めることが求められます。また、SNSやインターネットの普及を活用し、ユーザーとのコミュニケーションを強化することも重要です。紅白歌合戦の将来に向けて、さまざまなアイデアや工夫が期待されます。


